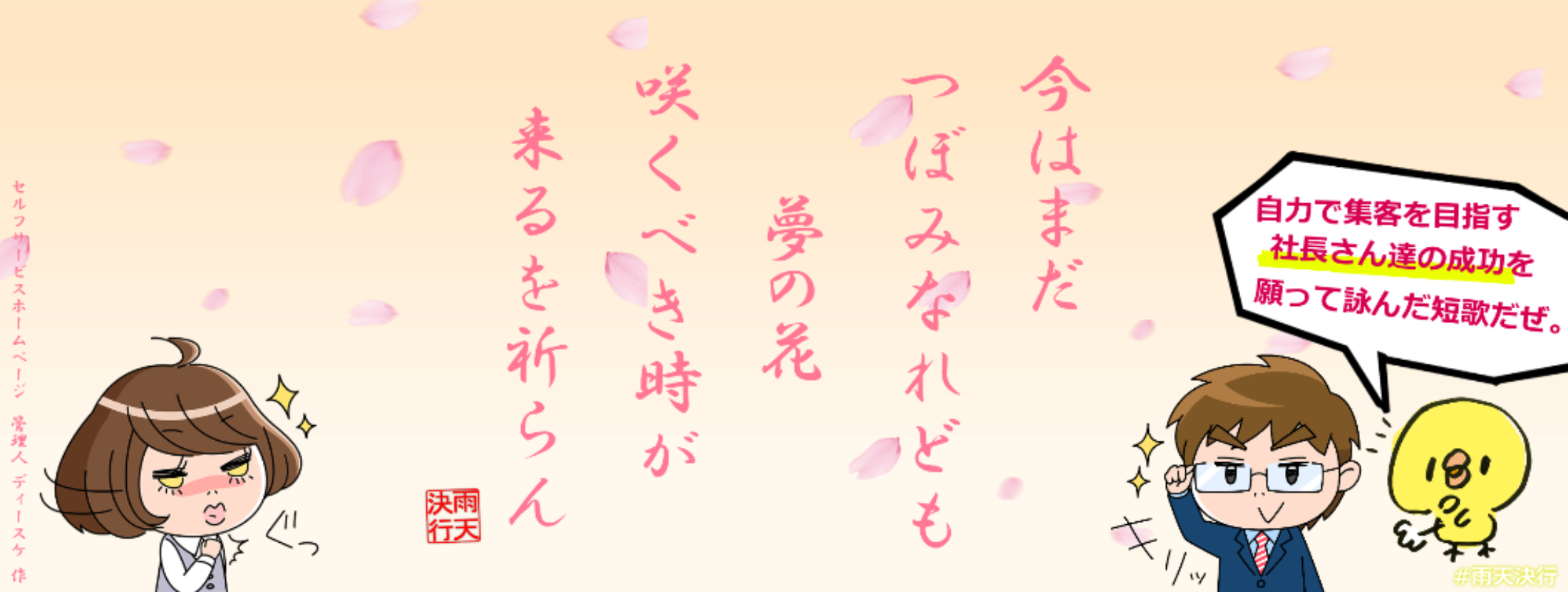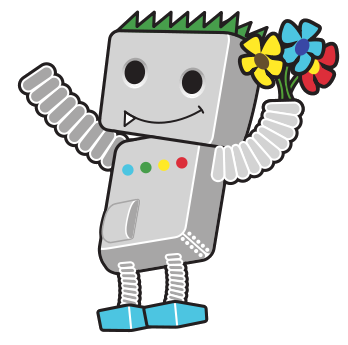さて、内部対策SEO講座として、ここまでタイトルタグの書き方や、メタディスクリプションタグの書き方について、説明してみましたが、いかがでしたでしょうか?
難しいと言うよりも、どちらかと言うと、面倒くさい…と思った人の方が多いんじゃないかと(笑)

そうなんです。SEO対策と聞くと、言葉の響きは難しそうに感じますが、実際の作業は、地味で、地道なモノ(笑)
むしろ、難しいのは、実作業ではなく、SEOの考え方の部分なのかと思うのです。SEOは、明確な答えがありませんし、ユーザーや、Googleの真意を探る必要がある訳ですから…
でも、この単純作業を、コツコツやることで、ユーザーにも、Googleにも理解してもらい易い(=SEO対策に強い)サイトが作れる訳です。
モノ作りにおいて「神は細部に宿る。」と良く言われますが、SEO対策も一緒。面倒くさいことほど、しっかりと丁寧に進めていきましょう!
さぁ、本日の講座は、タイトルタグ、メタディスクリプションタグと同じく、SEOにおいて、重要と言われている見出しタグについてご説明したいと思います。

ホームページ作成ソフトが無けりゃ、HTMLも、CSSも覚えなくちゃいけないんだから、どんだけ大変か想像できるだろ?
この講座の目次
見出しタグとは?
見出しタグというのは、言葉の通り、コンテンツ内部で使われる「見出し」のことです。
文字だけで構成された情報は、読者にとって、何が書いてあるのかを瞬時に判断するのは難しいですが、「この段落は、こんなことについて書いてありますよー。」って、ユーザーに視覚的に伝える役割を担っているのが、見出しタグです。
新聞や、雑誌、小説などをイメージして貰えれば、分かりやすいと思いますが、
見出しタグは、通常のコンテンツに使われる文字の大きさよりも、重要度の高いモノほど、大きな文字で表現されるのが一般的です。

ただ、視覚的に伝える役割と説明しましたが、特定エリアの文章・段落が、「何について書かれているのか?」文章構造を伝える意味合いの方が重要で、見出しタグでの本質的な役割だと言えます。
僕が公式に発表してる、検索エンジン最適化(SEO)スターターガイドでの説明も一緒に読んでみてよ。
見出しタグを使用して重要なテキストを強調する。
一般に、見出しタグはタグに囲まれているテキストをページ上の通常のテキストよりも大きく表示するため、ユーザーにとってはそのテキストが重要であるという視覚的な手がかりとなり、見出しテキストの下に続くコンテンツの内容について理解しやすくなります。
複数の見出しサイズを正しい順序で使用すると、コンテンツの階層構造が作成され、ユーザーがドキュメント内を移動しやすくなります。
見出しタグは、6段階もある?
Googleさんの公式の説明で、「複数の見出しサイズを…」という文章が気になった人もいるかもしれませんが…
実は、見出しタグは、その重要度に応じて 6つのタグを使い分ける必要があるんです💦

そう… つまり見出しタグというHTMLタグは、1つではないのです!

見出しタグの種類
<h1>1番重要な見出しタグ</h1> <h2>2番目に重要な見出しタグ</h2> <h3>3番目に重要な見出しタグ</h3> <h4>4番目に重要な見出しタグ</h4> <h5>5番目に重要な見出しタグ</h5> <h6>6番目に重要な見出しタグ</h6>
英語で「見出し」のことを、headingや、headlineなどと表現しますが、その頭文字である Hから始まる 6つのタグが用意されており、見出しタグとは、この6つのHTMLタグの総称なんです。
では、6段階用意されている見出しタグの中で、どれが 一番重要度が高いのか?と言うと… 数字が小さいものほど重要度が高くなります。つまり、1番重要とされるのが、<h1>となります✨
また、6段階ある見出しタグ、それぞれの意味合いは、文章構成でいうと以下のようになります。
- <h1> = 題
- <h2> = 部
- <h3> = 章
- <h4> = 節
- <h5> = 項
- <h6> = 小見出し

まぁ、使い分けについては、いつも通りホームページ作成ソフトに任せようや。
ホームページは、作文と同じ?
作文を書くのに、絶対的なルールってありませんよね?
起承転結がないと、作文は書いちゃダメ!のような厳格なルールはありませんから、ルールに縛られることなく、自分の自由なスタイルで書くとこができます。
ただ、作文を読む側にとっては、「読み易い」と感じる構成と、「読み難い」と感じる構成があるのも事実ですよね?
そして、「読み易い」と感じる文章は、構成がシッカリしているモノの方が多いのは、作家や、小説家でなくても想像できると思います。
例えば、題名が書かれ、そのストーリーが、1部、2部と分けられて、そして、1部の中に、1章、2章とストーリーが展開する… 頭の中でストーリーを追いやすく、非常に理解しやすい構造ですよね?
実は、ホームページのコンテンツ作りも、この作文と、ピッタリ一緒✨
どこでホームページの内容を、1部、2部と区切ろうが、1章、2章とストーリ分けてを展開しようが、逆に、全くストーリーを分割せず、思いつくままに書こうが、そこを縛る明確なルールはありません💦

ただ、ホームページの設計書であるHTMLを読む側の Google(=検索エンジン)にとっては、読み易い HTMLと、そうでない場合がある訳です💦
読みやすい作文の方が評価され易いのと同じく、検索エンジン側からしても、解読が難しくて、何を言いたいのか意味が分からないホームページの設計書よりは、シッカリと明確に文章構造が整理されている設計書を評価するのは、当たり前ですよね✨

見出しタグの正しい順序と、使い方
見出しタグを使わなくても、ホームページは作れるけど、検索エンジンや、ユーザーにとっても、分かりやすい文章を書くには、使った方が当然ベター。
もちろん、SEOの観点で言っても、見出しタグを使うことは必須と言えます。
でも、見出しタグの意味や役割を、ちゃんと理解して使わないと、逆に、記事の内容が分り難くなってしまう諸刃の剣…💦
理解し易い見出しを構成するには、見出しタグの使い方を理解する必要があるんです。

で、具体的な使い方と言えば、以下の 4つ。
見出しタグを使い方
- <h1>の次は<h2>。<h2>の次は<h3>と、番号順に使うこと。
- <h1>は、1ページに一個まで。
- <h1>以外は、何回使ってもOK。
- <h1>から、<h6>まで全部使わないといけない訳じゃない。

一例として、良い例と、悪い例を見比べてみてくれ… ちょっと極端な例だけど、きっと見出しの重要性を気付いてもらえると思うんだ。
正しい見出しの使い方例
理解し易い Hタグの使い方例
【 リンゴについて 】
1.名称
・学名
・和名・漢字
・英語名
2.植物学上の特徴
3.リンゴの歴史
・欧米
・中国
・日本
-ワリンゴ
-セイヨウリンゴ
4.生産
・栽培法
・樹形と台木
5.品種
・「ふじ」
wikipediaの見出しタグの使い方を参考にさせて貰ったんですが、とっても分かりやすいですね✨
見出しを見るだけで、どんな内容・ストーリーなのかが、ある程度想像できるから、読み手にとって、必要な情報がどの辺に書いてあるのか、瞬時に判断できますよね?

では、次は、間違った見出しタグの使い方例を見てみましょう。
ストーリー展開は、上記とピッタリ同じでも、受ける印象はまるで違うと言うことを体感いただけるはずです💦
間違った見出しの使い方例
間違った Hタグの使い方例
-リンゴについて
・名称
1・学名
・和名・漢字
-英語名
・植物学上の特徴
2.リンゴの歴史
・欧米
-中国
・日本
【ワリンゴ】
-セイヨウリンゴ
・生産
・栽培法
【 樹形と台木 】
3.品種
【「ふじ」】
見出しタグを、間違えて使うと、こんな感じになっちゃうんです…
書いてある内容、構成は一緒でも、見出しタグの使い方を間違えると、これだけ致命的な差が生まれるんだ💦
<h1>~<h6>まで、正しく使ってね!
見出しタグの使い方は人によって違う!?

前述した通り、見出しタグは、絶対に使わないといけないモノでもなく、また、使うとしても、<h1>から<h6>の全てを、使わなければいけない訳ではありません。
職業柄、ディースケも、いろんなホームページを徘徊して、HTMLソースを覗き見していますが、プロのWebデザイナーであっても、どの場面で、どの見出しタグを使うかは、人それぞれ。
<h1>は使っても、<h2>は使わないとか、<h1>は、全てのページで会社名を指定してたり、会社のロゴ画像を指定していたり… ホント様々です💦
別に、表現方法ですから、書き手の自由で良いのですが、果たして、これが読み手にとって、読み易いか?と言ったら、書き方、使い方によって大きな差異が生まれる訳です。
つまり、人それぞれ表現方法の違いが許されるからこそ、読みやすい作文を書く人と、読み難い作文を書く人が生まれると言うことです💦

でも、誰もが、読み手に分かりやすい文章を書けるとは言えないよな?
読み手に分かりやすい文章を構成できるのも、一つの技術であり、能力なのさ。
もし、SIRIUSや、賢威、Affingerと言った SEOに強いホームページ作成ソフトを使わず、WEB制作業者に依頼してたとしたら…
そのWEB制作業者が書くHTML(=文章)は、Googleにとって理解し易いモノなのか否か、どう判断すれば良いんだろう…。って、不安に思いませんか?

判断する方法は、残念ながら 1つ。自分が、HTMLの知識を持ち、そのWEB制作会社の作ったホームページのHTMLソースを見て、タグの意味に基づいて記述されているか?を、自分で判断する以外にありません。
何十万、何百万円と言う大金を払って、ホームページを作ってもらったとしても、決して安心はできないと言う事です💦
なぜならば、ホームページの品質は、費やした金額で決まる訳でなく、ホームページの設計書を書く、WEB制作業者の知識と表現力に委ねられているのですから。

当サイトが、ホームページ作成ソフトをお勧めする理由。
プロと言っても、そのWEB制作業者が、Googleに分かりやすいHTML(=文章)を書いてくれるかは、蓋を開けてみなけりゃ分かりません。
また、ホームページの作成経験の無い人が、HTMLを覚えただけで、検索エンジンにとって、読み易いホームページを作る事ができるかと言えば… かなり厳しいことは想像できますよね💦
日本語が話せるからと言って、全ての人が、読みやすく、分かりやすい文章を書ける訳でないのと同じ理屈です。

だから、当サイトでは、ホームページ作成経験の無い人でも簡単に使えて、検索エンジンにも理解し易いHTMLを書いてくれる、SIRIUSのようなホームページ作成ソフトをお勧めしているんです。
WEB制作業者の一人として、あるまじき意見ですが、
既に、ホームページは業者に依頼し、管理される時代は終焉を迎え、これからは、自分でホームページを運営し、品質を管理する時代である!
と、ディースケは強く思うのです。

さぁ、見出しタグの役割を理解してもらったところで、次の講座は、SEOに強い見出しタグの書き方をお伝えするよ。
-

-
SEOに強い h1タグと見出しタグの書き方・使い方
さて、前回の記事では、見出しタグの役割についてお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。 どんなに頑張って記事を書き、分かりやすく説明したつもりでも、見出しタグの使い方を誤れば、読者にも、Goog ...